摂津国
住吉郡を拠点に活動していた
「軍事的な氏族」で、
歌人として知られる
大伴旅人 (たびと) は
軍人としても有名で、その子・
大伴家持 (やかもち / 10歳) も父とともに筑紫国の大宰府に赴任。といいます。
当時、
筑紫国の大宰府は『遠の都 / ミニ朝廷』と呼ばれ、
倭国 (後の日本) の出先機関ような役割をし、
大伴家持 (やかもち) の父・
大伴旅人 (たびと) は大宰府の長官で
 白村江の戦い
白村江の戦いに向かった防人たちの軍
司令官でもあったようです。
* たびとは歌人で軍人
― (・・? ―?→
7世紀は
日本史の始点で『日本 (国号)・天皇 (称号)・大化 (元号) 』が用いられた時代

今日の令和という元号の源泉に云われています。

* 日本のナショナる意識が高まった時代
当時の倭国 (後の日本) は
摂津国と大和国に都を行き来しており、大和国は「内政の都」
 摂津国
摂津国は『外交の都』の役割をしていたようです。
― →
→
(・・! 意外にも?!
倭国が日本 (国号) を意識し、
日本初の元号 (大化) が使用されたのは摂津国の難波宮に都があった時代で、その後も
難波宮は『副都』や『外交的』な機能 / 役割をしていた。との事。
また、
難波宮があった
摂津国の一宮は
住吉社で、住吉 (すみのえ) の神は海的な「お社」で海外への航路神・
軍神の色を持っていたといいます。
摂津国
住吉郡を拠点に活動していましたので、その
『住吉 (すみのえ) 』という文字は → 後にも前にも ← 重要なキーワードになっているように思います。
―(・・? ―?→

遣隋使や遣唐使は住吉大社で航海安全祈願後、
住吉津 ~
難波津を経由して → 瀬戸内海 → 朝鮮半島や中国大陸へ向かったようです。
―(・・? ―?→

上町台地の『高台 = 大坂』にあったという。
→ 後にも前にも ← 住吉 (すみのえ) という文字は重要なキーワードに。
… 端的にいうと
端的にいうと  →
→
例えば?
豊臣秀吉いうと
 大阪城
大阪城を思い浮かべるけど?
自分の学生ころ教科書では織田信長と豊臣秀吉の時代 → 織豊時代は『安土桃山時代』と記載されていました。
織田信長は安土城
 豊臣秀吉
豊臣秀吉は
桃山城 (
伏見城) を内政の都に。
豊臣秀吉は京都の
桃山城 (
伏見城) を「内政の都」
 大阪城
大阪城を『外交の都』にしていたようです。

時代は飛んでいるけど

豊臣秀吉も →
西に東に ← 7世紀の
倭国 (後の日本) と似た政策をしていたように思います。
(・・? 関連かも?情報→
鎌倉時代の (前) 北条氏も
 安土桃山
安土桃山時代の (後) 北条氏も
伊豆国に政治の起点を持ちます。
ー↓─━ ─扉─
─扉─ ━─↓ー
━─↓ー
 時宗
時宗 (
ときむね) は
時宗 (じしゅう) を
立入禁止。
時宗 (
ときむね) は
伊豆国に源泉、
―(・・? ―?→
 ─伊予国
─伊予国 と
伊豆国 ─
7世紀は
日本史の始点時代
 伊予国
伊予国 と
伊豆国は 
西方と東方の
出入口 
なっていたように思います。
日本史の始点時代 →
倭国 (後の日本) のナショナる意識が高まった時代、摂津国の難波宮に都があったといいます。
伊予国 と
伊豆国 →
摂津国 は『
三島の里』になっており、その源泉は7世紀の『
白村江の戦い』にあると云われています。
三島 →

7世紀の
倭国 (後の日本) は朝鮮半島にあった百済 (くだら) を救済するため
白村江に向かいました。
―(・・? ―?→

時代は飛ぶけど


飛鳥時代の6世紀ころ、朝鮮半島の百済国から「仏教」が日本にやって来ました。
(・・; そのとき;
蘇我氏と物部氏による「崇仏排仏論争」が起きます。
結果、廃仏派の物部氏が崇仏派の蘇我氏に勝利し、

日本に初めて持ち込まれた仏様 (仏像) は
難波の堀江に棄てられました。
後ほど、
難波の堀江に棄てられた仏様 (仏像) を
本田善光という人が拾い上げ、仏様 (仏像) を信濃国に持ち帰り
善光寺 という寺名の起源に?! という
『説 / 伝承』も云われています。

それも
伝承ですが
、
ー ―…
―… ―…
―… →
→ →
→
(・・; 内容は複雑していますが;
時宗 (じしゅう) の一遍上人 は伊予国で生まれ、10歳のとき母を亡くし、14歳とき筑紫国の大宰府にあった浄土宗の寺院にて出家 → 25歳とき父を亡くし伊予国に帰国し、いったん僧侶を辞める / 還俗 → 33歳ころ再出家を決意し、信濃国の善光寺で―・・→
信濃国で踊り念仏を始めた一遍上人は、その後、全国各地を遊行 (念仏廻り) し摂津国で亡くなったと云われています。
一遍上人は 
 上記文の国に関与
上記文の国に関与  見えます!?
見えます!?
また、当時の善光寺は『どんな人も?』宗派を問わない寺であったようです。
… もう一度
もう一度  →
→
時宗 (じしゅう) は 伊予国に源泉、
時宗 (ときむね) は 伊豆国に源泉。
―(・・? ―?→
7世紀は
日本史の始点時代
 伊予国
伊予国 と
伊豆国は 
西方と東方の
出入口 
なっていたように思います。
(・・? 詳しくは解りませんが?
7世紀ころ伊豆国「辺り』が「中央政府」と『東方政府』の分岐点になっていたようで?

東国各地から集結した防人たちは次から次へと摂津国の堀江 (ほりえ) から小舟に乗り → 伊予国 → 筑紫国 → 朝鮮半島に出発して行く。その様子を見た大伴家持 (やかもち) は「彼らはもう二度と妻に逢えぬかもしれない。さぞかし望郷の念に駆られていることであろう」と? 防人たちの心中を思いやった1首? 思われます。
(・・? 時宗 (ときむね) と 時宗 (じしゅう) ?
伊豆国と伊予国 → 西に東に ← 出入口?─ ━
━
ともに  三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。
三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。
―↓―↓―
熟田津に
船乗りせむと
月待てば
潮もかなひぬ
今は漕ぎ出でな
━─額田王─━─
―↓―↓―
防人の
堀江漕ぎ出る
伊豆手船
楫取る間なく
恋は繁けむ
━─大伴家持─━─
さきもりの
ほりえこぎづる
いずてぶね
かじとるまなく
こひはしげけむ
― →
→


 熟田津 (にぎたつ) とは
熟田津 (にぎたつ) とは  →
→
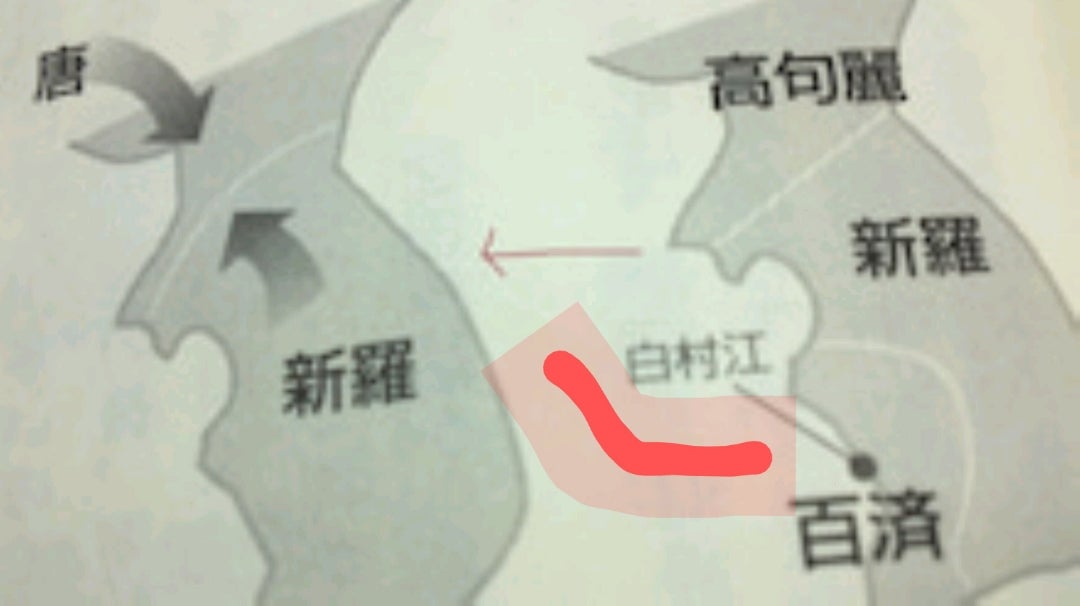
 ─扉─
─扉─ ━─↓ー
━─↓ー ―…
―… →
→ →
→ 白村江の戦い に向かった防人たちの心中を歌った代弁歌に思われます。
白村江の戦い に向かった防人たちの心中を歌った代弁歌に思われます。 ―…
―… →
→ →
→ 端的にいうと
端的にいうと  →
→ ─扉─
─扉─ ━─↓ー
━─↓ー ─伊予国 と 伊豆国 ─
─伊予国 と 伊豆国 ─
 西方と東方の出入口
西方と東方の出入口  なっていたように思います。
なっていたように思います。



![]() ―…
―… ―…
―… →
→ →
→![]()
![]() 上記文の国に関与
上記文の国に関与 ![]() 見えます!?
見えます!? もう一度
もう一度  →
→ 西方と東方の出入口
西方と東方の出入口  なっていたように思います。
なっていたように思います。 ━
━![]() 三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。
三島の里になっているので、その源泉は非常によく似ている? 思います。
 →
→












コメントを残す