2022/11/22
ー?→
あれは、
2代将軍・源頼家 (よりいえ) が幼い頃だった‥
ー・→
政子 :「武家の頭領、後継ぎなら、鹿くらい射とめて当然です。そのやうな、くだらない手紙、使いの者なぞ寄越すでない」
ー![]() →
→
政子は嫌がる頼家を無理やり出家させ、伊豆の修善寺に幽閉した。
ー・→
頼家 :「ここは、退屈でありますから、日頃わたくしに使えていた者達を見舞いに寄越してはいただけませぬか」
ー![]() →
→
23才 になった源頼家は、伊豆でお風呂に入っているところ、殺された‥ 北条家の者が? いう「うわさ」がたった。その後、3代将軍・源実朝も罠のような死に方をした‥ 振り返ると? 初代将軍・源頼朝も不自然な死に方をしていた。「源氏」の鎌倉幕府は3代で亡び ⇔「平氏」の北条氏が執権政治 (外戚政治) を行っていたようです。
政子は夫である源頼朝が亡くなると、出家して尼になっていた。そんな北条政子には「悪女伝説」がつきまといました。
*悪女伝説は儒学の視点が高まった江戸時代から? それまではなかったといいます。
源頼朝は北条政子が出産の度たび、浮気をしていました。それを知った政子は、浮気相手を木に縛って叩いたり、家を焼いたりしていました。
振る舞いの反面 ⇔ 弱い立場な女人、戦さや謀反で親を亡くした子に対して、政子はこまやかな気づかいを見せた。政子はなんとしても夫・源頼朝の築いた「武家社会」を守りたかったとされ。当時は「情よりも理」を選ばざるを得ない「武家政権」にとって危機がせまっていました。政子の手腕によつて ![]() 結束力は高まったと云われています。
結束力は高まったと云われています。
 ―…
―… →
→ →
→ ―…
―… →
→ →
→ ―…
―… →
→ →
→古代には、弓矢を作る「弓削部」、麻糸を績む「麻績部」、馬具を作る「鞍作部」、玉を作る「玉造部」、番犬を育てる「犬飼部」、南方の防人「久米部」、北方の防人「佐伯部」‥‥、鵜飼部、日下部 (くさかべ / 草壁)、日置部 (ひおきべ) など‥‥ 職業部があり、そのうち日置部という祭祀儀礼に関する職業部は、土師 (はじ) 氏が担当していました。
*日置は「火起」に通じ、日置族の長が土師氏。
最初ころ、日置部は太陽祭祀 (天体観測) を司り、暦に精通し、豊漁、豊作に通じていました。そして、太陽祭祀の使用道具である埴輪や土偶、土器製作に使用する『火』は製土の他、製鉄、 製塩にも通じ、やがて日置族は一部をシャーマン(太陽祭祀)に残し、製土、製塩、製鉄 → それに関連する職業部に通じて行きます。
彼ら (日置族) は、太陽の祭祀集団(土器職人)であると同時に武力集団(鉄器職人)のような役割をしていました。そして次代に、日置部 / 日置族は大和国家の新たな支配地へ中央から送りこまれた尖兵 (久米部や佐伯部) にも通じたようです。
また日置族は、もと海部族だった人々が多く、古代の海部族は「蛇 (ヘビ / 長)」をトーテム (蛇信仰) としていたので、蛇 ≒ 長 / 那珂 / 中、海蛇 ≒ 宇嘉 / 宇賀、久米や佐伯、などといった地名が日本全国「日置の里」近くに多く見られます。
ー ; →
 もう説とは
もう説とは  →
→ ─扉─
─扉─ ━─↓ー
━─↓ー ─扉─
─扉─ ━─↓ー
━─↓ー ―…
―… →
→ →
→ ―…
―… →
→ →
→ この度ブログは
この度ブログは  →
→ →
→



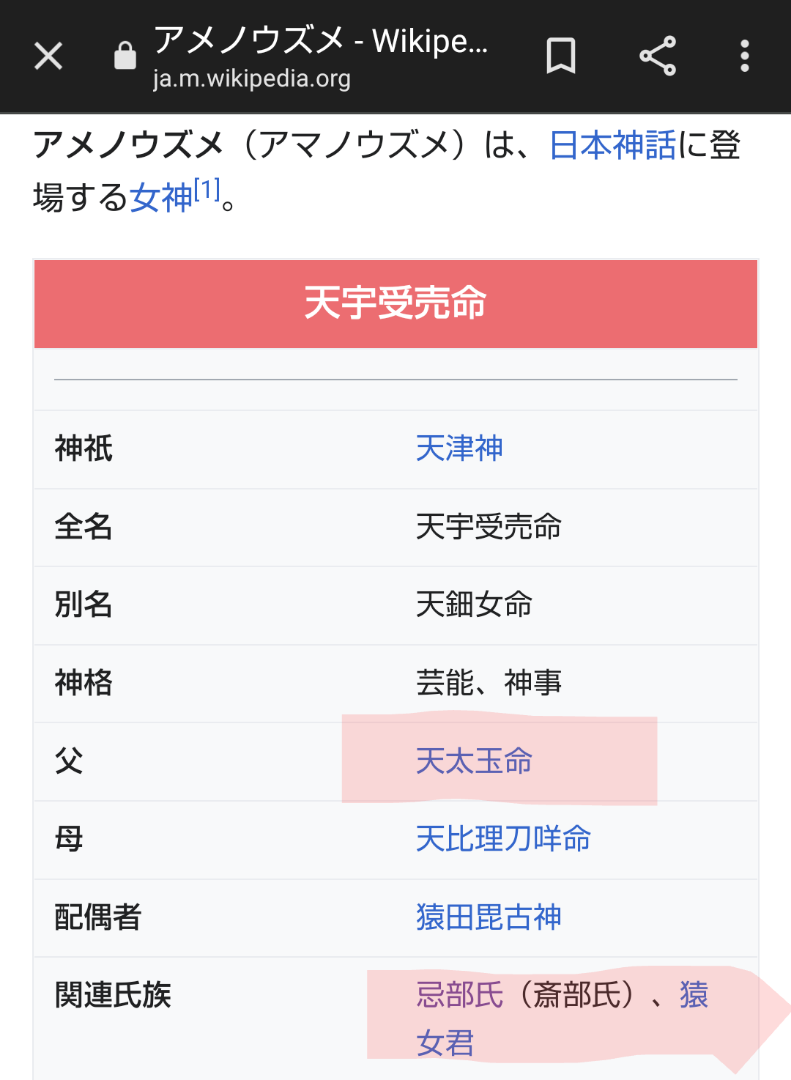










コメントを残す